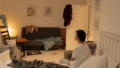毎日の基本の掃除にプラスする「1日1掃」シリーズ。
毎日少しずつ汚れているけれど、毎日掃除をするほどでもない。
そんなワンポイントを定期的に綺麗にすることで、住まいが隅々まで輝き始める新習慣をご紹介します。
所要時間を目安に、今日も1日1掃で住まいをピカピカにしていきましょう。
冷蔵庫をスッキリきれいに保つポイント
- 買物をして帰ったら、同じ食材が冷蔵庫に残っていた
- 買物先で「〇〇の在庫あったかな?」と迷う
- 冷蔵庫に何がどれだけ入っているか把握していない
- 使い切れずに処分する調味料があるが、それを忘れて何度も同じ物を買ってしまう
- 冷蔵庫の奥の方が見えない
- 同じストックが沢山ある
- 無料でもらった薬味が沢山ある
もし、これらに1つでも当てはまるものがある場合、今回の記事がお役に立つかもしれません。冷蔵庫を開けた瞬間、何がどこにどれだけあるか一目でわかる、そんな冷蔵庫はとても使いやすく快適です。今回は、冷蔵庫をスッキリきれいに保つ5つのポイントと、1回3分からできる掃除方法についてご紹介します。この記事を読み終わったら、できるアクションから1つ実行してみてください。
①冷蔵庫の中身を棚卸しする
現在、冷蔵庫に何がどれだけ入っているか把握していますか?もしも答えがNoであれば、まずは冷蔵庫の中身を全部出してみましょう。室内を涼しい状態にし、クーラーボックス等を使って冷凍食品が溶けないように注意して、すべての食品を一旦冷蔵庫の外へ取り出します。
ここで、賞味期限切れの食品があれば廃棄します。あまり使わなかった調味料や、いつも同じものを買ってかぶってしまうもの等、買物のクセがわかることもあります。スーパーでもらったわさびや醤油も、今使わないのであれば一旦すべて廃棄しましょう。「無料だから」という理由でもらっても、使う出番も無く賞味期限を迎えるならば、保管しておく必要はなくなります。
いつ購入したか分からない冷凍食材(肉、魚、野菜)は、体の安全・健康を最重視するなら廃棄した方が安心です。もったいないと感じるかもしれませんが、ご自身やご家族の体以上に大切なものではないはずです。次回からは、保存する際に保存袋やラップに日付を記入しておくと安心です。開封後数日以内に使い切るタイプの調味料も、しばらく使っていなければ廃棄します。必要な時に、一番小さいサイズを購入すれば大丈夫です。
冷蔵庫を空っぽにしたら、ここからがスタートです。濡らして絞ったクロス等で冷蔵庫内を拭き掃除します。冷蔵庫の掃除をしていなかった場合や、汚れがひどい場合は、パーツを1つ1つ外して食器洗剤で洗います。一気にやると時間がかかるので、メインの棚・扉収納・チルド室・冷凍庫というように、日を分けて1パーツずつ掃除していくといいと思います。
終わったら、冷凍食品から順番に食品を収納して完了です。
②冷蔵庫に食材を詰め込まない
食材・食品を冷蔵庫に戻した後、冷蔵庫の中を俯瞰的に見てみてください。一目で内容物が把握できますか?何がどこにあるかがわかりやすいでしょうか?使いやすい冷蔵庫にするポイントは、食材を詰め込まないことです。便利グッズや収納グッズを使わなくても、食品の量が少なければ、飾り棚のようにスッキリと全体を見渡すことができます。大家族や子育て中の世帯では難しいかもしれませんが、1人や2人世帯なら、冷蔵庫をパンパンにするほど食品を買い込まなくてもいいはずです。
まずは、普段の食事量、買物頻度、食材の嗜好(毎日食べたい物など)を把握し、「空っぽになったら買物へ行く」くらいの気持ちで、必要最低限の状態で暮らす練習をしてみてください。拭き掃除もしやすく、食品を探す必要もなくなります。災害時用の非常食・保存食は、冷蔵庫ではなく常温で、風通しの良い冷暗所にまとめて保存しましょう。
わが家の冷蔵庫は、おそらく傍から見るとガラガラの状態です。2人の食事量と週2~3回の買い物頻度を考慮すると、この状態が最適です。賞味期限を切らしたり、食品ロスが生じることもありません。
③食品の「保管方法」に従って保管する
生鮮食品以外の食品には、パーッケージの裏側に保管方法が記載されています。「開封後は冷蔵庫へ」「開封後はお早めに」「開封後は2~3日を目安に」「開封後は高温を避けて常温で」など保管方法の記載に従って、適切な場所へ保管をしましょう。特に、コショウ・醤油・液状のだし・ハーブティー・マヨネーズ・一味など、普段常温で保管している方も多いかもしれませんが、これらは「開封後は冷蔵庫へ保管」と記載されていることが多いです。
飲料や調味料・スパイスなどをすべて冷蔵庫で保管すると、食品が傷みにくく、キッチンスペースもスッキリ保つことができます。ナッツ、開封後のお菓子、果物、お茶等も、冷蔵庫へ保管すると鮮度が長持ちします。冷蔵庫の扉収納を活用して、これらをまとめて収納してみてはいかがでしょうか。
今まで食品の保管方法まで気にしていなかったという方も、これから食品を購入する際は、保管方法と賞味期限を合わせてチェックする習慣をつけてみましょう。「すぐに使いきれないし、この調味料は買わないでおこう」という判断もできるようになります。
④賞味期限の管理
保管方法とあわせてぜひチェックしていただきたいのは、食品の賞味期限です。生鮮食品は数日以内に食べきることが多いと思いますが、加工食品や調味料は、つい長期間保管しがちです。賞味期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではないですが、食品の鮮度は確実に落ちていきます。体の安全のためにも、食材の風味を楽しむためにも、賞味期限を目安にいただきましょう。
チェックするタイミングは、①購入時、②1週間に1回(乳製品、大豆製品、加工食品など)、③1ヶ月に1回(薬味、味噌、調味料など)、④半年に1回(保存食、常温の缶詰、レトルト食品、インスタント食品、ふりかけなど)が目安です。冷蔵庫を開くたびに、都度チェックするのが最もラクですが、習慣化できるまでは、予定表アプリやカレンダーに入れておくと忘れません。
賞味期限が近い食品は、できる限り早めに使い切ります。使い切れなかった食品や調味料は、潔く廃棄しましょう。そして、次は同じような食品を廃棄しなくて済むように、食品を買物する際によく考えて注意します。慣れてくると、普段の買い物にメリハリが出て、食品ロスも少なくなります。
冷凍庫に保管した生鮮食品も、食品によってそれほど日持ちしないものもあります。食品ごとの保管方法や消費期限の目安を確認し、「冷凍しているから安心」とは思わずに適切なサイクルで消費していきましょう。
⑤食品の在庫管理をする(おススメ)
いろんなアプリや、冷蔵庫自体に在庫管理機能が付いているものもあるようですが、シンプルで使いやすい管理ツールとして「Google Keep」アプリがおススメです。スマホ、PCどちらからでもログインできます。「Google Keep」には、主に①メモ機能、②チェックリスト機能があります。私は、「食材在庫」をメモ機能で、「食品買うモノリスト」をチェックリスト機能で管理しています。
ます、①メモ機能のタイトルに例えば「食材在庫」と入力し、本文スペースの上から順に箇条書きで食品食材の在庫リスト+数量(残数)をすべて書いていきます(例:納豆3、ヨーグルト1.5、食パン5)。野菜系、大豆・乳製品系、調味料系、保存食系、果物、パン、肉・魚などわかりやすように、おおよそのグループごとに並べると見やすいです。食材在庫を「チェックリスト機能」を使って管理をしていた時もありましたが、「在庫の有無」と「買うor買わない」の判断がつきづらかったので、今はメモ機能を使っています。
コピペもできるので、リストの順番はいつでも変えられます。最初はとても面倒に感じるかもしれませんが、一旦リストアップが完了すると、次回からそれを修正・削除・追加すればいいだけなので、在庫が一目でわかってとても便利です。
次に、②チェックリストのタイトルに例えば「食品買物リスト」と入力し、本文のリストに買いたい食品をリストアップします。チェックリスト機能がついているので、買ったらチェックを入れて消し込みができるようになっています(例:✅食パン5枚)。これも、買ったor買っていないが一目でわかります。買物が済んだ商品のリストにチェックを入れて、①の「食材在庫メモ」にも追記しておきます。また、次に買物に行く前にも、最新の「食材在庫」「食品買物リスト」に更新しておきます。
最初は手間に感じるかもしれませんが、これも慣れてしまえば無意識にできる習慣です。買い忘れや同じ物を買ってしまうことは、まず無くなります。献立や食費予算管理もしやすくなります。在庫管理が苦手な方も、ぜひ試してみてください。
1回3分から始める冷蔵庫の掃除
一度冷蔵庫の中をリセットし、適切に買物し、パーツを1つずつ洗ったら、基本的には外側と内側を時々拭き掃除するだけでスッキリきれいな状態に保つことができます。初心者の方は取扱説明書を見ながら、取り外せるパーツを1つずつ外して食器洗剤とお湯で洗いましょう。一気に外すと、どこのパーツか分かりづらくなることがあります。まずは1回3分を目安に、パーツを1つ綺麗に洗いましょう。
自動製氷機が付いている場合、製氷機水入れケースは1~2日おきに洗って入れ替えるか、氷を使わない場合は自動製氷をオフにして水入れ容器も洗って外しておきます。製氷機のフィルターを買い替えていなければ、ネットでフィルターのみ売っているので交換も検討しましょう。機種によって扱いが異なるため、すべてお使いの冷蔵庫の取扱説明書に従って行ってください。
普段の掃除方法は、濡らして絞ったクロスなどで、冷蔵庫の内側・外側をサッと拭きます。毎日触るものなので、特に手で触る場所は汚れや雑菌が付きやすいです。頑固な汚れがついていない場合、特に洗剤は必要ありません。冷蔵庫内は、食品や液体の汚れが付着し、カビになることもあります。時々絞ったクロスでサッと拭くか、パーツを外して洗いましょう。
1回3分あれば、徐々に冷蔵庫を綺麗に保つことができるようになります。ぜひ、お掃除習慣の1つに取り入れていただければと思います。
今の暮らしに合った冷蔵庫を使う
冷蔵庫の中を整理して掃除もしたけれど、冷蔵庫が使いづらい・古いと感じる場合、冷蔵庫を開けて「形名」と「製造年」を確認してみましょう。ネットで調べると、リコールや修理・注意喚起情報、電気代(省エネレベル)、後継商品、口コミなどの情報が出てきます。もし、今の冷蔵庫が大きすぎたり、小さすぎたり、使いづらさを感じる場合は、冷蔵庫へ買い替えるタイミングかもしれません。
家族の人数、家族の身長、キッチンの構造やスペース、料理をする頻度や内容、よく買う食材などを振り返ってみてください。冷蔵庫を購入した当時と今では、使い勝手も変わっているかもしれませんね。10年以上前の冷蔵庫だと、部品劣化や故障のリスクが高まり、冷蔵庫の省エネレベルも低い製品が多いです。大切なことは、「今」の暮らしに最適であること。家族全員が使いやすく、機能的で、できる限り省エネであれば嬉しいですね。
今の暮らしに最適な冷蔵庫のイメージがついていない場合は、重視したいポイントを整理し、優先順位を付けましょう。置き場所に適したサイズ、容量、形状、色、予算などを決める際、品ぞろえ豊富な大型電機店などで、展示品のサイズ感や使い勝手を確かめるのもおススメです。左右開き、チルド室、冷凍庫の大きさなど、それぞれのこだわりを確認できるので安心です。その再、冷蔵庫の置き場所の採寸は事前に必ずしておきましょう。今とは別の場所に置く場合、冷蔵庫用のコンセントの位置も必ず確認します。省エネレベルは、毎日の電気代に直接影響しますので、できる限り高水準のものがトータルでみると経済的です。
欲しい冷蔵庫が決まったら、「価格.com」でその商品を検索し、古い冷蔵庫の引き取りと一緒に、安心できそうな店舗から購入するといいと思います。実店舗で購入するよりも安く購入できる場合がほとんどです。頻繁に買い替えるものではないので、慎重に検討して最適な冷蔵庫を選びましょう。
毎日体に摂り入れる食品によって、私たちの身体が作られています。何を、いつ、どれだけ食べるのかを意識し、新鮮で栄養価の高い食材をいただけることに感謝しながら、日々の生活を過ごしていきたいですね。今回の記事で、みなさんの冷蔵庫がよりスッキリ、綺麗に、快適な存在になればいいなと願っています。